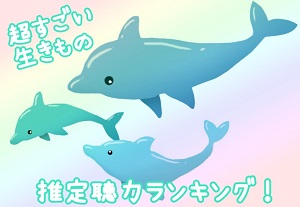「味」って舌で感じるイメージですよね?
指でさわるだけでは味ってわからないです。
甘味とか塩味とか酸味とか、苦味とか旨味とか。
おいしいお肉や甘いスイーツを楽しめるのって舌のおかげなんですよね。
すごくあたりまえな話なのですが。。。
なので、舌で五味(甘味・塩味・酸味・苦味・旨味)を感じるのは正解。
ただ、舌ほど鋭敏ではありませんが、口腔(口のなか全体)で感じているみたいです。
食べものを摂取するときの最初の通過点である「口」全体で味を感じとる仕組なんですね。
味を感じ取る器官って「味蕾」(みらい)とよばれています。
蕾(つぼみ)みたいな形の感覚器官だから「味蕾」
その「味蕾」の数が多いほど味覚に敏感になるというわけですね。
というわけで、味を繊細に感じわけられる生きものを「味蕾」の数をもとに独自にランキングします!
👑生きもの味の繊細さランキング
さっそく味の繊細さランキング発表です!
星5つ⭐⭐⭐⭐⭐が最高ランク。
味蕾の数の多さをもとに評価しました!
結果はつぎのとおりです!
| 👑 味の繊細さ ランク | 生きもの | 味蕾の数 | 甘 | 塩 | 酸 | 苦 | 旨 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⭐ | ヒト | 10,000個 (成人5,000個) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 五味を識別 加齢で減少 発達は文化的影響大 調理により味の複雑化を楽しめる |
| ⭐⭐ | ウサギ ヤギ 草食動物 | 15,000〜 17,000個 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | 草を選別 栄養価・安全性を識別 毒素判別のため苦味が高感度 |
| ⭐⭐⭐ | ブタ | 15,000個 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 雑食性 多様な味を識別 人間よりも味覚が鋭い |
| ⭐⭐⭐⭐ | ウシ | 20,000〜 25,000個 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | 毒素判別のため苦味が高感度 糖分のちがいを識別可 |
| ⭐⭐⭐⭐⭐ | ナマズ | 200,000個 | ○ | ✖ | ○ | ○ | ○ | 全身に味蕾あり 味覚で獲物を探知 水中の微量成分も検知可 水中に塩分含むため塩味不要 |
20万個という桁ちがいな味蕾の数をもつナマズが1位です!
おめでとう!ナマズ!
というわけで、それぞれの特徴を解説していきます!
ヒト
⭐星1つはヒトです。
星1つですが、じつはヒトはかなり味に敏感な生きものなんです!
理由は火を使った調理。
ヒトに近いチンパンジーも調理の概念を理解しているかも!?と考えられています。
実験によるとチンパンジーは加熱した食べものが好きみたいなんです。
でも火を扱えない。
火を使った調理ができるのってヒトの大きな特徴なんですね。
調理によって味覚が複雑に変容・拡張されて五味以上の味わいも体験できるのはヒトのみ。
たしかに大人になると味蕾が減るぶん味に鈍感になってしまいます。
でもそのかわり、ヒトは調理という能力を身につけます。
調理によって味覚を拡張できるので、味蕾の数は減りますが、じつはより複雑化した味わいを感じとれるのかもしれませんね。
ヒト
✅加齢により味蕾が半分に減少
✅調理により五味以上の味わいも体験可
ウサギ・ヤギ・草食動物
⭐⭐星2つはウサギ・ヤギ・草食動物です。

ウサギやヤギに代表される草食動物は生存戦略として肉ではなく草(植物)を食糧に選びました。
草って走って逃げませんので、争ったり戦ったりするする必要もなくいつでも食べられます。
ただ、草って栄養価がとっても低め。
なのでたくさん食べる必要があるんですよね。
たくさん食べると、なかには「毒」のある草もでてきます。
そこで、ウサギやヤギは苦味やえぐみを感じる味蕾が発達したわけですね。
ちなみに、ウサギやヤギが食べると危険なのは玉ネギや長ネギやニラやニンニク。
硫化アリルっていう成分が完全NGで、食べると生命にかかわるようです。
生物によって「毒」って変わるんですね。
ウサギ・ヤギ・草食動物
✅草をたくさん食べるので苦味で栄養価や安全性を選別
ブタ
⭐⭐⭐星3つはブタです。
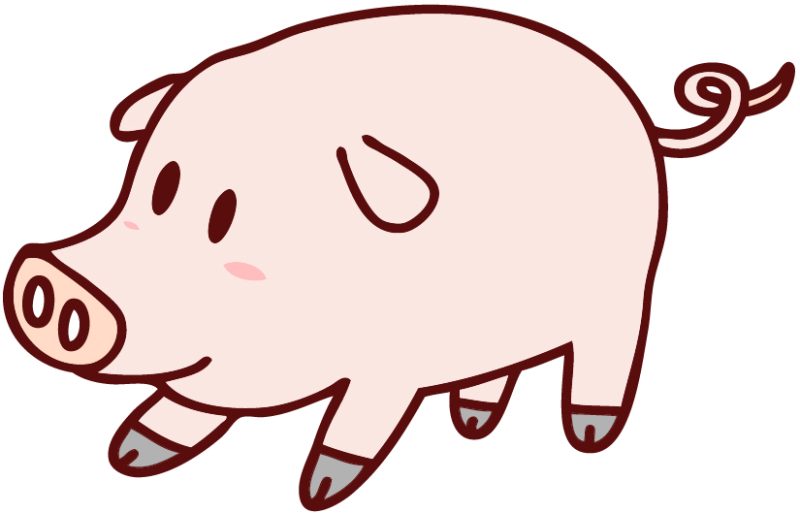
可愛いブタさん。
なんでもたくさん食べちゃいそうですが、じつは人間より繊細でグルメな感覚をもっているんです。
味蕾の数はヒト(成人)の5,000個より多くて15,000個!
しかも脂味(脂肪の味)まで鋭敏に感じとれるという、まさに味覚の探究者と呼ぶにふさわしい生物なんです。
脂味は「第六の味覚」と言われていて、ブタの味覚はその脂肪酸の種類まで選別できるほど高精度。
また、五味のなかでは甘味と旨味の感度がとても高いのが特徴です。
なので大好物は糖度の高いサツマイモやリンゴ、バナナやイチゴ、メロンやスイカなどなど。
ほぼ果物。
めちゃくちゃ甘党ですよね。
とくにスイカは別格で、食べるとテンションMAXになるみたいです。
ちなみに、ある養豚場での実験によると、シフォンケーキをあげてみたところすさまじい食いつきだったとか。
甘味はもちろん脂味もたっぷりなのでまちがいないおいしさですよね。
ブタの味覚もすごいけど、シフォンケーキを作れるヒトってホントすごい。
テンションMAXでおいしく食べれるってほんとうにしあわせなことですよね。
ブタ
✅脂味(脂肪の味)を高精度で選別
✅甘味と旨味もきわめて高感度
ウシ
⭐⭐⭐⭐星4つはウシです。
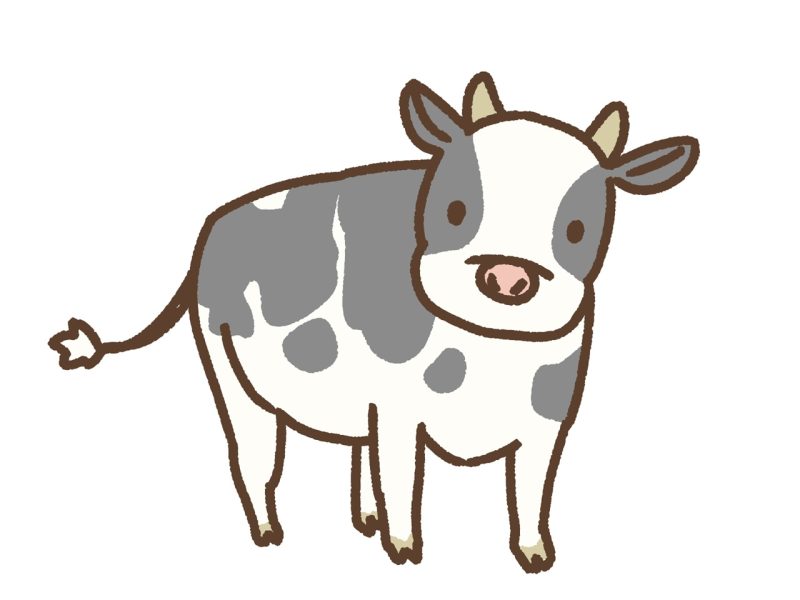
ウシも草食動物ですが、星2つのヤギとはちょっと異なります。
ヤギは木の葉や低木や雑草など多様な草食。
ウシは草専門で、ヤギと同じく苦味を感じる味蕾のほかに甘味を感じる味蕾も発達。
草に含まれる炭水化物の甘味=エネルギー源としてより栄養価の高い草を選別するためなんです。
たしかにあの大きい体を維持するにはたくさんエネルギーが必要ですよね。
反芻動物でもあるウシは、第一胃(「ミノ」とよばれる部位)で微生物によって発酵された脂肪酸などの栄養素を摂取。
ウシにはそれらの栄養素を検知する受容体が口腔や消化管内にあるかも?と言われているんです。
舌で味わったあとも胃や腸でも味わえるってお得ですよね。
ウシは鋭敏な甘味センサーを駆使して大量の草を摂取。
よく咀嚼して体内の微生物に発酵させることで必要な栄養素を得る。
ヤギも胃が4つある反芻動物ですが、ウシは胃の大きさがヤギの10倍で100ℓ。
体が大きなぶん胃袋のスケール感もすごいですよね。
ウシ
✅草をたくさん食べるので苦味で栄養価や安全性を選別
✅甘味を高感度で識別
✅甘味を高感度で識別
ナマズ
⭐⭐⭐⭐⭐星5つはナマズです。
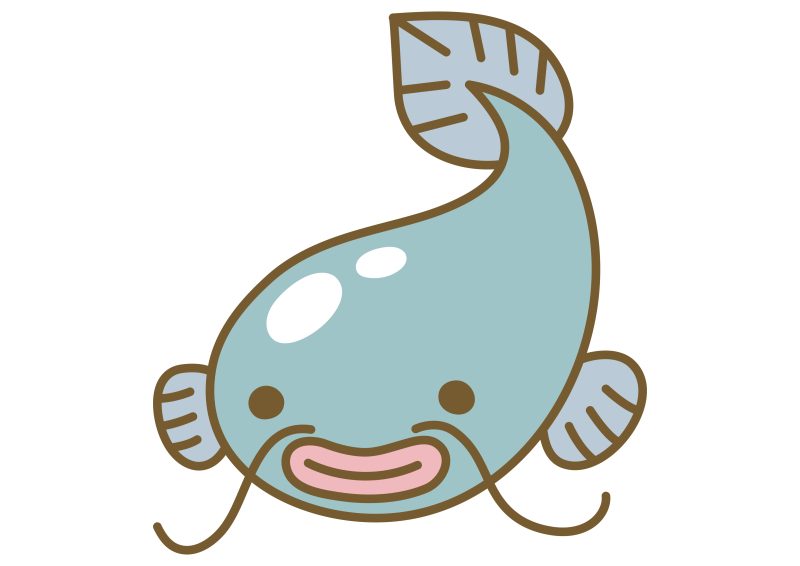
ナマズの味蕾の数はヒト(成人)の40倍の200,000個!
40倍!
しかも20万個!!
超高感度で超繊細!
どんな味でも明確に選別できちゃうんです!
ただし、ナマズの味覚はヒトのそれとはまったく別物。
食べものを味わうためではなく、探知機としての味覚なんです。
マナズは濁った水のなかで生きるので視覚が退化。
濁って視界ゼロですから、とうぜん不要ですよね。
そのかわりに味覚が鋭敏に発達。
空間認識、距離測定や獲物の追跡に味覚が使われるわけです。
20万個の味蕾が、口腔内はもちろん、ヒゲや皮膚、ヒレや尾にまでひろがっているんです。
とくにヒゲ。
獲物の位置をさぐる左右のヒゲには1mm²あたり15個以上の味蕾が密集。
ここからは推測ですが、ヒゲの長さが10~15センチ、直径3~5ミリとすると、ヒゲの表面積は400〜700mm²、ヒゲ1本あたり6,000〜10,500個の味蕾が集中していることになります。
ヒゲは2本あるので、合計12,000~21,000個!
ヒゲの味蕾だけでウシ1頭に匹敵する数になるという驚異の高精度センサー!
しかし味覚で空間を認識するのってどんな感じなんでしょうね。
視覚はまぶしければ目を閉じれるし、聴覚はうるさければ耳をふさげるけど。
水中だと味はにじんで伝わるでしょうからシャットアウトできないし情報量が多くてたいへんそう。。。
ナマズ
✅味蕾の数は20万個!
✅全身に広がる味蕾で空間認識可
🍚番外編~じつは意外!?味覚のない生きもの
生きものはみんな、食べて消化して栄養を摂取して生きています。
ですので必ず味覚がありそうなんですが、じつは進化の過程で味覚をなくした生きものもいるんです。
それはイルカやクジラ。
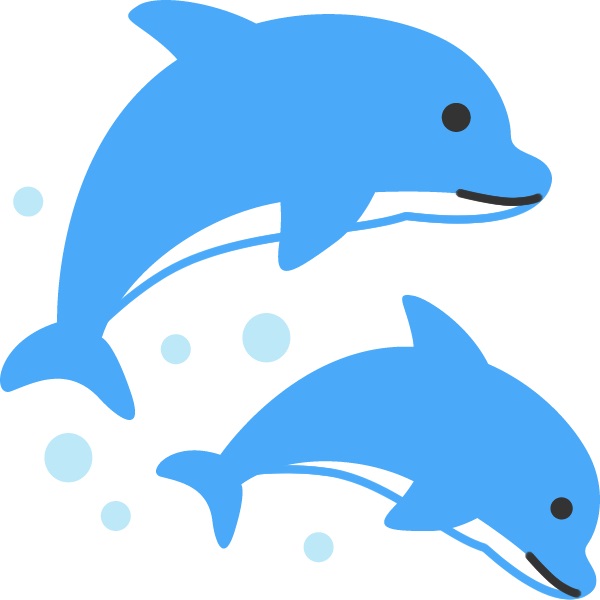
イルカやクジラは味がわからないと言われています。
海にいるので塩味の識別は不要。
陸にいるわけではないので腐敗物を食べる恐れなし。
腐敗物を味覚で選別する必要がないわけですし、そもそも咀嚼なしの丸呑みなので味覚そのものが不要。
鼻が頭のてっぺんにあるので味覚に密接にかかわる嗅覚も退化。
ナマズとまったく異なって、味覚に頼る必然性がない環境にあるわけなんですね。
イルカは味覚の代わりに音波(エコーロケーション)を使って獲物の種類や位置を正確に計測。
味覚も感覚器官の一つ。
生きるための戦略としてどのように感覚を活用するか。
生きものによってまったく異なるのがおもしろいですよね。
さいごまで読んでくださってありがとうございました!
_(._.)_